第6回講義レポート 日本有機農業研究会理事長 魚住道郎氏「有機農業による提携と自給で豊かな暮らしの社会を築く」
2023.02.13以下、事務局がまとめた伊那谷有機農業塾第6回のご講演(日本有機農業研究会理事長 魚住道郎氏)の要旨です。
有機農業に携わって50年以上

私が有機農業を始めたのは大学生の時、1970年のことでした。神奈川県厚木市で実験的に取り組みをはじめました。思っていたよりも上手くできたことで、有機農業が自分の生涯のテーマになると感じたことを覚えています。
4年後の1974年、茨城県八郷町の消費自給農場「たまごの会」の創設に参加したことをきっかけに就農。1980年、同町内で有機農家として独立し、現在に至ります。有機農業に携わってから50年以上が経ちましたが、奥が深く、まだまだ未解明なことが多いと感じています。
現在、長男夫婦と私たち夫婦の二世代で取り組んでおり、耕作面積は約3.5ha。野菜300a、大豆麦30~40a、水田15aを栽培するほか、平飼鶏500羽を飼育しており、約100世帯に供給しています。
有機農業は生物多様性の実現に重要
50年以上、有機農業に携わってきて強く思うことは、“有機農業は生物多様性の実現にとって重要”ということです。
まず、生物多様性を持った自然環境の実現には、針葉樹と広葉樹が適度に混じり合った「豊かな森」が必要です。落ち葉などが育んだ腐植を雨水が通過することで、ミネラル豊富な地下水が生まれます。その地下水は湧き水となり川を形成し、田んぼの動物や昆虫、プランクトン、微生物などを育てます。さらに、海に流れて、海藻やプランクトンを育て、藻場を豊かにします。
ただ、これだけでは、生物多様性の実現にとって“ある要素”が足りません。それは「里の有機農業」です。有機農業を行うことで、里の田畑が動物や昆虫、プランクトン、微生物などにとってより生息しやすい環境になります。また、有機の田んぼについては、そこで繁殖したプランクトンやそこで生成した腐植が川と海に流れていけば、その環境がより豊かになります。
こうしたことから、有機農業に取り組んでいけば、従来の豊かな日本の生物多様性が復活できるだろうと思うのです。実際に、有機農業を実践しているところでは、復活してきています。
生産者と消費者が支え合う「提携」

私が理事長を務める日本有機農業研究会では、こうした森・里・川・海の生物多様性を重視しながら、有機農業を社会に広げるために活動を行っています。
研究会は一楽照雄により52年前に設立されました。一楽は全国農業協同組合(JA)中央会のトップとして、日本農業の近代化をリードする一方で、近代化しても所得が向上しない、食味が落ちる、農薬による農家への健康被害や作物の残留農薬の課題も感じていました。そのような中で、課題を克服するための手法として有機農業に注目し、有機農業研究会を立ち上げました。
有機農業研究会で、創設以来提唱され続けてきたのが「提携」です。これは生産者と消費者が「農」と「食」に関して支え合う関係のことを言います。
有機農業は土づくりや栽培技術の習得に時間が掛かるなど、安定して収入を得ることが難しい面があります。それを乗り越えるために、消費者は有機農家が年間を通じて農産物購入の約束をすることで、農家の家計を支える。一方で、有機農家は年間を通じて消費者に農薬や化学肥料を使用しない農産物を直接供給することで、消費者の安全・安心な食生活を支える。このように有機農家と消費者がお互いに支え合う「提携」の輪を、有機農業研究会は社会に広げていきたいと考えています。
消費者にとっての食の安全保障という点で、提携への注目が高まっています。最近は大地震や大型台風などの災害が頻発していますが、災害時に都市部ではスーパーなどで食料不足になる問題が起こっています。仮に、しばらくは簡易な非常食でお腹を満たせるかもしれませんが、必ず野菜や肉などを欲するようになります。そのようなときに、「提携」している農園があれば、農産物を直接送ってもらうことができます。実際に魚住農園でも、阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害時に、食料を待つ子どもたちや消費者に野菜を送り、とても喜ばれました。
また、最近はウクライナとロシアの戦争で、農作物の価格が高騰しているということでも、食の安全保障が脅かされています。この点についても、地域の有機農家と「提携」の関係を結んでおけば、安定的な価格で農作物を確保することができます。
援農は農家と消費者の双方に利点

「提携」のなかで、重要な要素となるのが、“援農”です。援農とは、農家の生産現場に消費者が足を運び、農作業を手伝うことです。「提携」の関係にある消費者による援農は、農家が消費者と直接つながる機会を持つことができ、モチベーションアップにもなります。
一方、消費者にとっての援農の利点は、自分で農園を所有していなくても、援農を通じて自分の食べる農産物の生産に関わることができる点です。食べ物を自給することが難しい都市生活者にとって、これはとても意義のあることです。
また、体験的な価値もあります。実は、土に触れることを渇望している都市生活者は多くいます。魚住農園にも、多くの方が援農に来てくれますが、中には80才を超える方もいて、そのようなとてもご高齢な方が元気よく活き活きと農作業をされている姿を見ると、都市生活者にとって、土に触れることはかけがえない体験なのだと実感します。
手作りアイデア農具で、援農しやすい環境を

援農者は農作業に不慣れな人が多いことも事実です。魚住農園でも定植のラインが曲がったり、適切な株間で定植されなかったりといったことがあり、後から修正する作業はとても骨が折れます。こうした課題に対応し、農作業に不慣れな人でも効率よく正確に楽しく作業してもらうために、私は“手づくりアイデア農具”の開発に力を入れています。
まず紹介したいのが、植え穴明け器、通称「コロコロ」です。これは苗の定植用の穴を空けるものです。丸太の中心に穴を空け、そこに棒を通して車輪のようにしたうえで、キャリーケースのように、コロコロと転がして使います。丸太には木の枝などを切ってきて、先を尖らせた爪を例えば株間30㎝間隔になるように打ち付けます。そうすることで、畑の上を転がすと30㎝の一定の株間で、一定の深さの植え穴を開けられるというわけです。その穴に小松菜やチンゲン菜、京菜、ベビーリーフ、レタス等のセル苗を植え付けていけば、農作業に慣れない援農者でもまっすぐに苗の定植ができます。
玉ネギ定植用の特殊ヘラも自信作です。これは歯欠けになり不要になった熊手の先端部に少し切り込みを入れて2本の爪を作ったものです。この特殊ヘラの2本の爪の間にタマネギの苗を挟み込むようにして土のなかにグッと押し込めば、しっかりと深く定植できます。タマネギの苗は浅く植えると冬場に霜柱で持ち上げられてしまうので、しっかり深く植えなくてはいけないのですが、数千本も植えていると次第に指先が痛くなってきます。しかし、この特殊ヘラを使えば数千本の苗の定植でも、楽々と行えます。
非常に体力が必要な水田除草の負担を軽減する手づくり道具も開発しています。木の棒に、鋼線やギザギザとした歯、Uボルト、タイヤチェーンを取り付けたものです。これを、畔から手で引っ張って使います。「円月雑草法」と私は呼んでいる除草法で、株間も全面除草できます。水田の中に入らなくてよいため、服が汚れず、身体が冷えることもありません。子どもでも引っ張ることができます。
援農で福島の被災者支援も
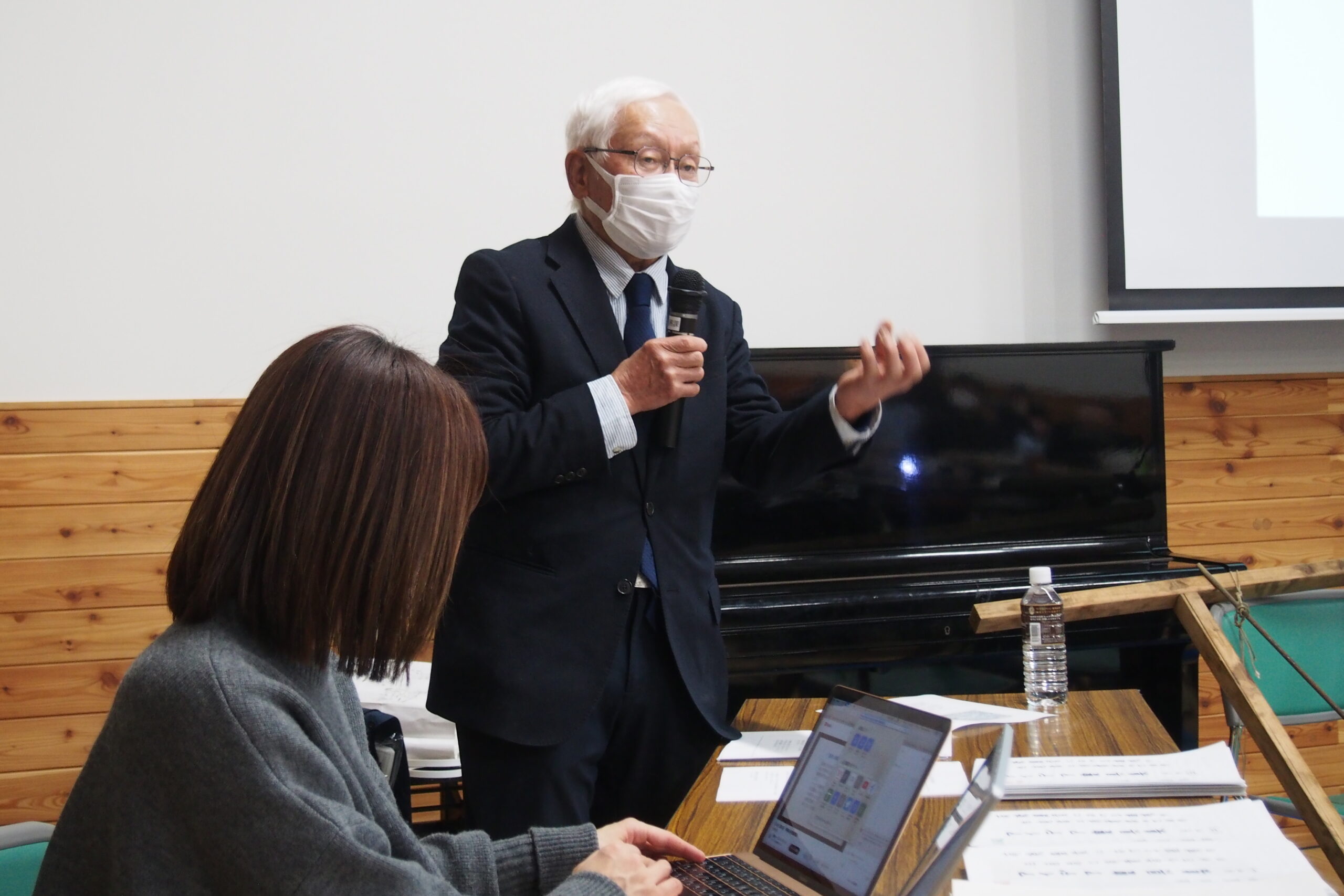
こうしたアイデア農具なども使いながら、援農が面白くなってくると、個人の魚住農園の外に出て、社会で試したくなります。それで、東日本大震災の時には、原発の放射能漏れで被災した福島県二本松市の会員を支援するため、東京の消費者などに集まってもらい、援農の取り組みを行いました。カンパでトラクターや各種農機具を購入し寄贈したほか、一緒に農作業も行いました。プラソイラーで畑を深く耕し汚染されていない下層の土を表に持ち上げ、表面の放射能汚染の低減を図ったり、ニンジンの収穫をしたり、夏野菜の支柱を片付けたりしました。援農者の作業効率向上のため、自慢の手づくりアイデア農具も持っていき、作業に使用しました。
援農で訪れた二本松市の農家からは「一時は耕作をやめようかと思ったけれども立ち直ることができた」と嬉しい声もいただきました。コロナ禍で活動を中断していますが、今後、再開できればと思っています。
中断していた活動の再開と言えば、「全国有機農業の集い」です。これは有機農業研究会の会員が1年に一度、一堂に会して交流を図る全国大会で、2020年に水俣市で開催して以来、コロナ禍で開催できていませんでしたが、今年ようやく再開することができそうです。場所は援農に行っている福島県二本松市で、2月25・26日に開催予定です。今後はこうした全国大会を開催するなど会員間の交流を促し、有機農業を通じた「提携」と「援農」を一層社会に広げていきたいと思っています。
